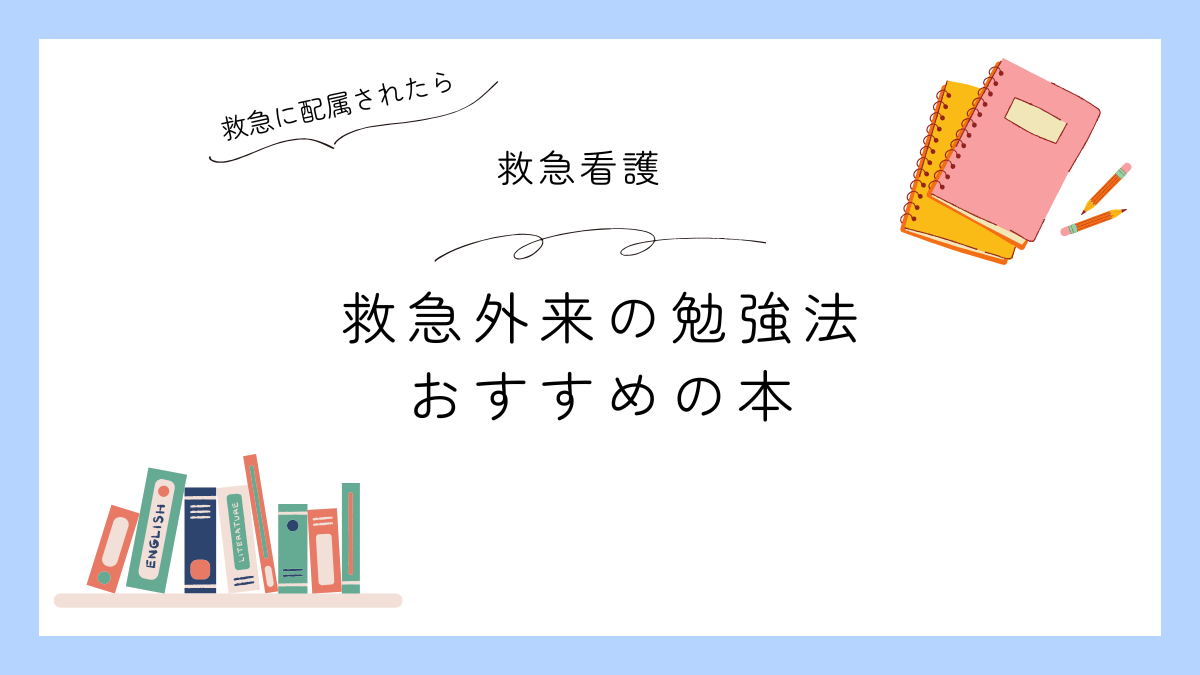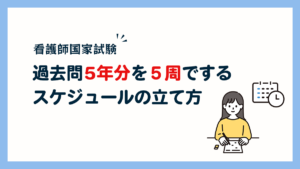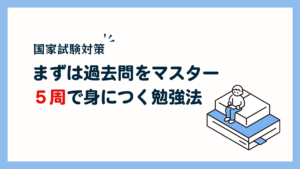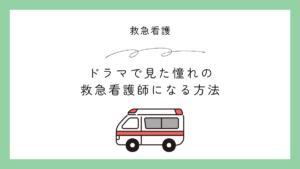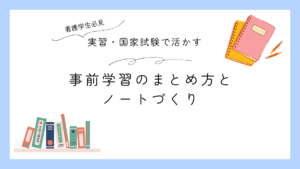救急外来で働いたことがないのに、救急外来に配属と言われ「やっていけるか不安…」と感じていませんか?
救急外来は少し特殊な部署です。私自身も初めて救急外来に配属されたとき、「テンポの早さについていけるのか?」「何を勉強すればいいのか?」など不安でいっぱいでした。
この記事では、そんな不安な気持ちを少しでも軽減できるように、救急外来でスムーズに働くために必要な勉強方法について解説していきます。
- 救急外来に異動になった看護師
- 救急外来に配属された新人看護師
- 救急外来で働くことを目指している看護学生
救急外来で求められることを学び準備しておくことで、不安がグッと軽くなるはずですので、ぜひ最後までチェックしてください。
救急外来と病棟の違いは?
救急外来と病棟は患者さんへのアプローチが違うため、勉強する内容にも違いがあります。
まずは救急外来と病棟の違いを知ることが大切です。
| 項目 | 病棟 | 救急外来 |
|---|---|---|
| 患者の流れ | 診断を受け治療が始まる | 診断に必要な検査や診察を受ける |
| 看護の役割 | セルフケアの介助や、状態の観察など継続的なケア | 急変対応や初期対応 |
| 業務のスピード | 比較的ゆっくり | 非常に速い、判断が早さが求められる |
| 緊急度 | 比較的安定している | 症状が悪化している状態で来院するため、緊急度が高い |
救急外来では、来院された状態から治療が始まるまでの診断や緊急処置が行われる場所です。
診断は医師が行いますが、検査や処置がスムーズに進むよう、ある程度診断を予測ができる知識が求められます。
違いを知っておくだけでも、救急外来で求められる看護が明確になり、気持ちが整理されます。
救急外来に入る前に勉強しておきたいこと
救急外来に入る前に、最低限押さえておきたい勉強内容は以下の4つです。
時間がない中でも、要点を絞って効率よく学びましょう。
基礎看護技術の再確認
バイタルサインの変化にいち早く気づきアセスメントする力は、救急外来では必須です。
状態が変化しやすい救急外来では「フィジカルアセスメント」や「観察ポイント(意識、皮膚、呼吸など)」は基本なので必要です。
救急では、採血、点滴、導尿など普段から行う看護技術はもちろん、挿管介助や胸腔ドレーン挿入の介助など、医師の処置介助も多くありますので、基本的な看護技術の手順を再度確認しておくことも大切です。
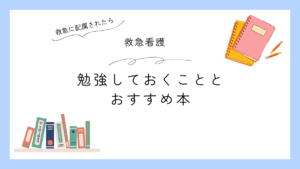
重症度・緊急度を理解する
救急外来では、状態が不安定な患者さんが多く来院するため、重症度や緊急度を素早く判断する力が求められます。
そのために、重症度・緊急度を判断できる指標を勉強しておくと良いです。
重症度の判断では、qSOFAやショックの5徴候といった指標が活用できます。
緊急度の判断には、救急外来のトリアージで使用されるJTAS(日本緊急度判定支援システム)を活用すると良いです。
優先順位を判断するためにも必要な知識になります。
ABCDEアプローチ
救急外来では、患者さんと最初の接触時にABCDEアプローチを行います。
ABCDEアプローチは迅速かつ効率的に緊急度を判断でき、それぞれ「A(気道)」「B(呼吸)」「C(循環)」「D(意識)」「E(全身観察)」です。
評価は、生命に関わる生理機能をAから順番に評価します。
救急では基本知識に入るため、評価方法を勉強しておくことが大切です。
急変時の対応
救急外来では、状態が変化しやすい患者さんが多いため、CPRの手順、BLS・ACLSのガイドラインなど、基本的な急変時の対応を勉強しておく必要があります。
また、緊急時に使用される薬剤(救急カートに置かれている薬剤など)について勉強しておくのも良いです。
緊急性を伴う疾患やよく救急で来院する疾患
救急は科目に関わらず、状態が悪化した患者さんが来院するため広範囲の勉強が必要です。
しかし、始めから多くの疾患を勉強するのは難しいです。
まずは、以下のような緊急性を伴う疾患やよく救急で来院する疾患について勉強しておきます。
- 大動脈解離
- アナフィラキシーショック
- 心筋梗塞
- 脳梗塞・脳出血
- くも膜下出血
- 食道静脈瘤破裂
- 胆嚢炎・胆管炎
また、救急外来では来院時に診断がついていないケースがほとんどで、最初は症状しかわからないことがほとんどです。
お腹の痛み、胸の痛み、意識障害、呼吸苦など症状に伴う疾患にはどんなものがあるか調べておくと、働き始めてからも少し余裕を持って働くことができます。
現場で出てからの学び方
救急外来は、勉強するだけで業務できるものではなく、実際の現場で得る学びも多くあります。
展開が早く、そのスピードに戸惑うこともありますが、スピード感については経験することで慣れてくるため、「見て・聞いて・真似する」が何よりの勉強です。
救急外来の1日の流れを知る
バイタル測定して、清潔ケアをして…の病棟とは違い、救急外来は患者さんが来てからが始まりです。
トリアージ、救急搬送の受け入れ、処置介助、搬送など病棟とは違う多様な業務があります。
患者の入れ替わりが激しく、情報収集のスピードと判断力が求められるため、実際勤務をしてみて、自分に足りないところは何か知りましょう。
先輩の動きを観察する
救急外来では、最初はわからないことも多く、判断に迷う場面が多いかもしれません。
そんなときは、先輩看護師の声かけや動きを観察することが大きな学びになります。
特に、観察のタイミングや優先順位のつけ方はとても重要です。時間の使い方ひとつで、患者さんの状態の変化を見逃してしまうこともあります。
先輩がどんな視点で判断しているのかを意識して見ることで、自分のアセスメント力も少しずつ磨かれていきます。
気になることがあれば、落ち着いたときに「どうしてあの判断をしたのか?」を聞いてみるのも良い学びになります。
視野を広く持つことが救急外来看護のコツ
救急外来では、1人の患者に集中しすぎると他の急変や新規患者に対応できません。
「視野を広く、先を読んで動く」ことが、救急外来看護の重要なスキルです。
複数患者を見る力をつける
救急外来は患者さんの入れ替わりも多く、注意することがたくさんあります。
- 患者さんの状態の変化
- 検査や処置に行く
- 状態に合わせてベッドの移動
- 搬送の情報 など
そんな中でもリーダーは全患者さんの把握が必要で、また担当しながら、他の患者さんの検査や処置の介助を手伝うこともあるため、複数の患者さんを見る力は必要です。
始めから完璧を目指さす必要はない
救急外来は知識も技術も必要とされ、経験が少ないと大変だと感じることが多いかもしれません。
しかし、救急外来はチームで動く場所です。
人員の配置が少ないため、多重課題も多くみんなバタバタしていますが、タイミングを逃すと患者さんの状態にも関わります。
できないことに不安になるよりも、わからないことは素直に聞き、必要な情報を報告・連携することの方が大切です。
救急外来の不安は準備と経験で乗り越えられる
最初のうちは「スピードに追いつけない」「急変対応や重症患者さんの対応が怖い」と感じることがあるかもしれません。
でも、基礎を学んでおくことで、現場での学びも加速します。
少しずつ知識と経験を積んでいけば、救急外来の勤務にも慣れ、自分の成長も感じられる日が来ます。
不安な気持ちが少しでも自信に変わりますように応援しています!